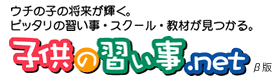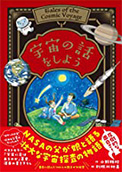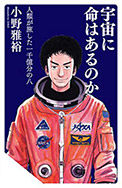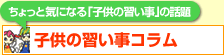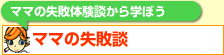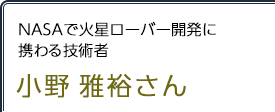 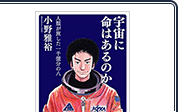 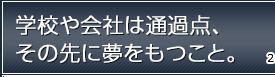 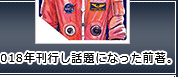
宇宙というテーマ以外でも、感動や興奮を伝えることが大人の使命と言えますか? 僕は学校で習う歴史は、ひたすら年号とか人の名前を覚えるのが大嫌いでした。漢字ひとつ間違えると減点とか意味不明で(笑)。でも本で読む歴史は大好きでした。文学も、読書は好きでも国語は嫌いでした。例えば作者が伝えたいことを80字で伝えなさいという問いがありますよね。80字でまとめられるなら作者は本一冊を書く必要なんてない。都合よく問題にするためだけに、文学や歴史はわざとおもしろくなくなっている。これは理科にも同じことが当てはまるのかもしれません。ノーベル賞受賞した物理学者リチャード・ファインマンが言った「もしも科学がおもしろいと思えなければ、それはあなたの先生が悪いのだ」という言葉があります。多分その通りでしょう(笑)。 教える人は子どもに大きな影響を与える存在ですね。ロサンゼルスは終息に向かっているようですが日本はコロナ禍がまだ少し続きそうです。制約の多い中で、どうしたら前向きに過ごせるでしょうか? 星空を見上げるのはどうでしょう。夏になると木星や土星も見えてきます。初めて望遠鏡で見て感動するのは月のクレーターと土星の輪。土星や木星は小さな望遠鏡でもハッキリと見られます。土星を初めて見た時は、「すごい!図鑑と同じだ!」と興奮した覚えがあります。音楽もCDで聴くよりLiveですし、スポーツもテレビを観るより本物を見るほうがいい。宇宙もインターネットで画像を閲覧するより、自分の肉眼や望遠鏡で観るほうがいい。できれば見上げる時に、空に関心のある大人が傍にいてほしいですね。 書籍の中で『ロケットの技術が戦争に利用された。いや技術者が夢を叶えるために戦争を利用したのかもしれない』…という歴史の観方には、ハッとさせられました。 宇宙ってキラキラした夢として語られがちですが、それだけではないんです。子どもに夢を…といってもキラキラした側面だけ見せればいいわけではない。世の中は綺麗なことばかりではないことを包み隠さずに全部曝け出して伝えた上で、ポジティブなメッセージを発信する。この本を作るうえでもそこは外せないと思って取り組みました。こういう問題には答えがないんです。学校の試験のように、覚えればクリアするものではない。大事なのは自分の頭で考えること。「あなたはこれをどう思いますか?」という投げかけをして書籍では締め括っています。問題意識をもって考えていくべきことでしょう。 では最後に、小野さんと同世代の親御さんへ向けて、教育とは?について何かメッセージいただけますか。 子どもに興味を持たせるには、まず大人から。子どもに勉強をさせたければ親も勉強が好きでないとダメでしょう。大人が興味もないものを子どもにだけ押し付けるのは違うと思います。親が興味をもつことに子どもは影響を受けます。使い古された言葉ですが、夢をもつことは大切。何かを長くがんばり続けることはシンドイですが、夢があれば越えられると思います。「これだけは諦められない」というものがあるからこそ頑張れる。諦めないと言うより、夢が僕を諦めさせてくれないという感覚に近いので、僕は「夢が僕を放さない」と言います。小さな頃に持った憧れや夢は強い。周りの大人が興味を持って、それが子どもに伝染して…夢を持てるといいですね。いい学校、いい会社に入るための勉強は目標達成したらそれで終わり。単子眼的なことを越える大きな目標があると、頑張り続けられると思います。 ---ありがとうございました! 2021年5月リモートによる取材・文/マザール あべみちこ 小野 雅裕 書籍紹介
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
子供の習い事トップ > ブログ・コラム・特集 > シリーズ・この人に聞く!第186回 > 3
|
||||||||||
|
|
||||||||||