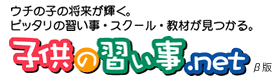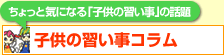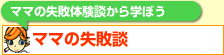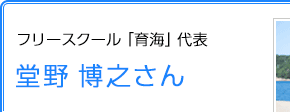 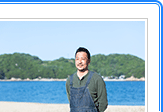 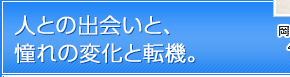 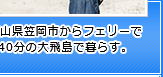
定時制高校では、どんな生活でしたか? もう、これが大変で大変で(笑)。人間関係、コミュニケーションスキルが全然育っておらず小学校2,3年生で止まっていたので、わからないことを素直に人に聞けず、失敗を恐れて周りの観察ばかり。買い物に行っても自分にどんな服が似合うのかすらわからない。店員が近づいてきただけで全身から汗が噴き出ました。いろいろ失敗を繰り返しました。生活費を稼ぐためのアルバイトも、1日休むとズルズルと無断欠勤をして辞めてしまったり。 自意識過剰のお年頃ですから尚更ですね。何が心の拠り所になりましたか? 定時制の仲間は不登校やヤンキーでみんな心根が優しかった。ひとり暮らしが珍しかったから僕のアパートがたまり場。様子を見に来てくれたりしてずいぶん救われました。学校ではバレー部に入部。先輩や先生に認めてもらえるのがうれしくて、誰よりも早く練習場に行って熱心に準備したり。定時制高校の4年間、バイトと学校でいろんな経験ができました。 岡山の定時制高校を卒業後、市内の高校で28年間職員として勤務されたとか。 校務技術員、いわゆる用務員さんとして最初は肢体不自由児の生徒たちが通う養護学校で4年間。その後、転勤して全日制高校へ。2つ目の学校では、まだ先生になろうという気持ちがあって通信制大学を目指して勉強していました。でも全日制の教員は、自分が理想としない先生ばかりでした。不登校ややんちゃをする子にも、僕がされてきた対応に終始する教師がそこらじゅうにいた。果たして僕が学校の先生になって、そんな指導ができるだろうか?と、職員室は僕がいる場所ではないと感じて、勉強が手につかなくなり大学進学はあきらめました。 憧れていた職業の捉え方が変わったのですね。 オレは一生用務員の仕事をしていくのだろうかと思い始めた時、僕をよく理解してくれる教育相談の先生から、こう言われました。「堂野さんが学校の先生になりたいと思ったのは、何か肩書がほしいと思ったんじゃないか。学校の先生というのは、ただの印に過ぎない。今の堂野さんにできないことは、先生になったからといってできるわけがない」と。その言葉にハッとして、学校の先生としてでなくひとりの人間として、できることがあるかもしれないと前向きに捉えることができた。用務員という立場でも、生徒とは出会えるし、僕がなりたかった先生、つまり人として憧れの大人をここで実践すればいいんだとわかった。それから学校に馴染めない子の話を聞く機会がどんどん増えていきました。 3年前に独立されて、岡山県の離島・大飛島に移住。不登校の子どものために「育海」を開かれました。何がきっかけでしたか? 遡ること用務員時代の97年に、自分の不登校経験を書いた詩画集「あかね色の空を見たよ」を出版し、それが話題になって映画化されました。それをきっかけに全国各地から依頼され400回以上講演をしたり。本職は用務員でも、ライフワークがそちらに引き寄せられました。その後、岡山にある私立高校から、専属の教育相談員としてきてほしいと声が掛かり、私立校職員に転職しました。教育相談員と兼任で生徒会、入試広報、学校法人の経営にも関わるようになり、山間部の学校で減少気味の生徒募集の意味もあり、通信制課程も立ち上げました。生徒が集まりやり取りしているうちに、通信制の単位はレポートとスクーリングで取れてしまうのですが、それは教育としてどうか?と。課外活動の拠点がほしいと思ったのが始まりです。 なぜ離島を選ばれたのでしょう? たまたま瀬戸内海の島に廃校があると聞いて、行ってみたら築25年の小学校はなかなか素敵でした。この島で、この校舎があれば、ぜったいいい教育ができると確信しました。島の管轄は笠岡市で、当時の笠岡市長へなんとか校舎を使わせてほしい、と島のビジョンをプレゼンにいったら、無償で使っていいと。それから最低月一のペースで通信制の生徒を連れて通い続けました。3年間通ってくれた子どもたちが卒業するタイミングで、僕が私立校を辞めることに。これからどうしようかなと思っている矢先、笠岡市で「地域おこし協力隊」募集を知った。なんとかして島であの教育を続けたくて、協力隊に応募して島で活動するという流れになりました。 |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
子供の習い事トップ > ブログ・コラム・特集 > シリーズ・この人に聞く!第189回 > 2
|
||||||||||
|
|
||||||||||