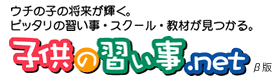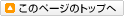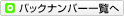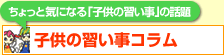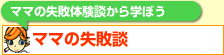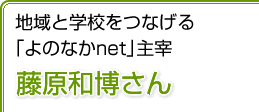 ![[よのなかnet]は、“新しい日本人”のライフスタイルを模索するサイト。](./img38/3p_title2.jpg) 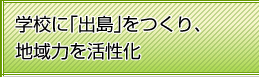 ![[よのなかnet]は、“新しい日本人”のライフスタイルを模索するサイト。](./img38/3p_title4.jpg)
教育を変えていく解決策として、何をしていくべきでしょう? 学校に「出島」をつくるんです。僕が推進している「よのなか科」でやっていることは、週1コマでもいいから地域の人が授業に参加して子供達と一緒に学べるようにする。異なるカルチャー、異なる考え方、異なる技術や知恵が交流する場になるわけです。もう一つは、毎週土曜日に教員以外のボランティアに勉強を教えてもらう「土曜寺子屋(ドテラ)」。これも「出島」の一種。 地域社会での人材の活用の仕方、これからますますニーズが高まりそうです。 元三井物産とか、元三菱商事とか、そんな企業時代の肩書きがまったく通用しないのが地域社会。名刺を取っ払って、元**会社という肩書きのない人を迎え入れよう。それが、「学校支援地域本部」の役割でもあります。ボランティアとして参加してもらい、算数とかテニスとか囲碁とかを子供達に教えてもらう関係をつくる。中学生の頃は特に子育てが難しくなって、自分の母親のことを「くそババァ」とか言う時代。教員にも反抗的だったりしますが、近所のおじさん、おばさんとナナメの関係を結ぶことで、違う「つながり」が生まれますよね。 オープンスクールのような何ヶ月か一度の公開授業ではなく、PTAのような強制ボランティアでもなく、地域と学校がゆるやかにつながる「出島」構想が広まると素晴らしいですね。 年に一度の公開授業なんて意味がない。毎週毎週公開され、大人と子どもが一緒に学ぶ[よのなか]科の授業が真に学校を開いていくんです。土曜日や放課後も開放して、大学生や塾の講師を含めた地域の教育資源の方々が寄り付く島をつくる。地域本部があれば、学校と外部との仲介役にもなってくれるでしょう。 では最後に、習い事を考える親へ何かメッセージをお願いします。 親と子の縦の関係ではなく、お姉さん役お兄さん役おじさん役おばさん役というような(利害関係のない第三者との)ナナメの関係づくりを誰に頼むか考えるのが親の役目。縦の関係より、ナナメの関係で子どもは勇気づけられるものなんです。ナナメの関係が欠乏すると、ついつい守りに入ってしまう。勇気をもてず、自尊感情が低くなる。ナナメの関係を誰とどのようにネットワークするか、つなげるか、を考えてほしいですね。
---ありがとうございました! <了> 
活動インフォメーション
「つなげる力」 まったく違う要素をつなげることで、新しい人生が開ける! 公立中学と超進学塾サピックスを合体させた「夜スペ」 中学生と社会をダイレクトにつなげた[よのなか]科 どのように発想し、行政のしがらみの中でどのように障壁をクリアし、 プロジェクトを発展させていったか?この本を読めばわかります! ケータイのメル友って、本当の友だち? 友だちって何だろう?を小学校の3~4年生から読める言葉で問いかけます。 大好評の前作『キミが勉強する理由』(朝日新聞出版)とともに、お子さんに読ませてみて下さい。利きますよ(笑)! |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
子供の習い事トップ > ブログ・コラム・特集 > シリーズ・この人に聞く!第38回 > 3 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||