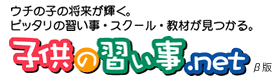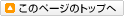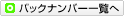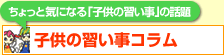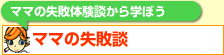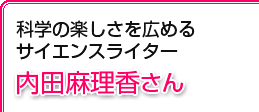  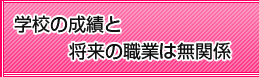 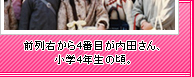
あまり親を手こずらせるようなお子さんではなかったのでしょうね。 そう思っていたのですが、自分の子を見ているとよく似ているので、そうじゃなかった!と気づきました(笑)。「やれ」といわれることはやらなかったですし。でも、それをやる方向へどうナビゲートするかなんですね。その点はうちの両親は長けていた。私は理解がはやかったから、学校では優等生でした。でも研究者は普通の人が通りすぎるようなところで立ち止まって考える。学校での成績と将来の仕事というのは関係ないと思いましたね。おとなからみてドンくさいな~という子のほうが、将来何か成し遂げるかもしれません。今は、ちょっとこだわりがある子に何らかの病名をつける傾向もありますが、昔の科学者でいうとアインシュタインもニュートンも相当変わっていましたから平均化されないことも大切かもしれません。 子ども時代のユニークさをどうキャッチできるかですね。内田さんは専業主婦をされていた時期もおありで、仕事に復帰されるきっかけがweb「カソウケン」の立ち上げでした。 大学院時代に結婚をして中退後、そのまま専業主婦になりました。夫の転勤の可能性も高く、上の子も病気がちでしたが続けて二番目の子を出産。でも何か社会とつながりがほしくて、エネルギーが余っていたんですね。それで「カソウケン」は普段の専業主婦をしている私の生活と、これまで培ってきた科学を結ぶ視点で何かできないかと思い、HPを作ってみました。 やっぱりエネルギーが溢れていらっしゃったんですね。科学の情報をどんなふうに届けたいと思いますか。 子どもから大人まで「理系ではない」人に、どれだけ科学のおもしろさに関心をもってもらえるかです。科学技術の本というのは理工系書のコーナーにあって、わざわざ興味のある人しか行かない。どちらかというと科学アレルギーのある方に「意外とおもしろかったよ」と言ってもらえる本を作ったり、基本的に関心のない人に振り向いてもらうにはどうしたらいいかのアウトリーチ方法を知るために大学院に入学し直し、それをテーマにしています。科学者と市民の懸け橋になるような活動を研究しているところです。 では、習い事を考えている同世代の親に何かメッセージを。 飢餓感が好奇心を育てると思います。草木と同じで水をやり過ぎると腐ってしまう。足りないくらいのほうが、やる気が出るのではないでしょうか。特にこんなに情報が溢れている時代ですから。
---ありがとうございました! <了>
活動インフォメーション
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||
子供の習い事トップ > ブログ・コラム・特集 > シリーズ・この人に聞く!第41回 > 3
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||