 |
■先生は神保町の地で34年も作文研究所を続けていらっしゃいますが、
どのようなきっかけで始められたのですか?
僕は大学時代、建築が専門でした。外側、いってみれば器を作る仕事です。
でも、教壇があって机があって。その器に教育があるわけじゃないんですね。
例えば、東大寺や法隆寺はなぜ今なお建築が残っているかというと、建物の構造が強かったわけでなくて、その時代時代の人々がその建物を残そうという意識をもっていたわけです。
その意識とは?と考えていくと、それは「言語」で、「言語」による構築物が重要なわけです。「言語」は硬直化してはいけない。流動化でき、可変性があって、意味の拡大ができるのが「言語」。それと人との関係が教育の本質だと、僕は思います。
■コミュニケーション論みたいなテーマの書籍も世の中には多いですが、
もっと深く掘り下げて「個人が内包する言葉」ということですか?
70年代は「個人は個人になれるか」あるいは「なぜ自立を求めるのか」という問いかけの時代でした。その時代のウオッチャーになろうと僕は決めた。
まだ20歳で学生でしたが作文研究所を始めたわけです。34年前のことです。
■その当時、どうやって生徒さんを募集されたのですか?
 ガリ版で刷ったチラシを巻いたり、通信教育がメインでしたね。というのも、20歳そこそこの若造でしたので(笑)。当時、入会金2000円、
月会費1000円で、課題を与えて添削して返送してというスタイルでしたね。 ガリ版で刷ったチラシを巻いたり、通信教育がメインでしたね。というのも、20歳そこそこの若造でしたので(笑)。当時、入会金2000円、
月会費1000円で、課題を与えて添削して返送してというスタイルでしたね。
そのうち「私は死にたい」と書いてくる生徒がいて、アドバイスレターという手紙を返して文通のようになっていった。
名づけて文通対話教育。そのうち、その親も参加されたりして。気付いたら10年間くらい手紙をやり取りしていた。教育とカウンセリングは一致しています。僕は教え込もうとは思わない。
■作文研がユニークな教育なわけがそこにあるわけですね。
今の学校では、どうしても作文の書き方ハウツーになっていますが、
作文研はそれとは違いますよね?
子どもが子どもなりの視点で世の中を捉えて考えて、どう生きようかと思っていることに私も向き合い、子どもは書いていること自体で自分と向き合い、僕はその場に立ち会って、また自分自身とも向き合う。これお互いが、合わせ鏡のような感じで無限に広がっていくの。奥が深い(笑)。
10年間は通信教育で頑張っていこうと腹を決めたので、生徒とは会わないと決めていました。会わないでどういう風に生徒との関係が深められるか。
言葉の力でどこまでできるかを実証したかった。人生とは実験の繰り返しです。
おかげさまで、どんどん生徒は増えていきました。
■そういうことが求められていたわけですね?アドバイスレターのような作文添削が。
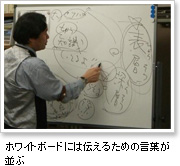 そうですね。 そうですね。
英語や数学みたいに添削しやすいものもありますが、「何を好んでこういうことをやっているんだ?」と友達にも当時言われました(笑)。
でも、皆がやるものは皆がやるわけです。僕は、皆がやらないものをやろうと。
でも、やっているうちに、これってスゴイことだなと気付いたのです。鉱脈みたいに掘っていくうちに深みにはまっていくような。
だって、10人生徒がいれば10人の作家を相手にしているわけですから。それぞれの思いを読み解いていかないとアドバイスはできません。
|
 |