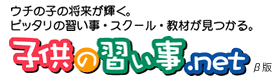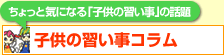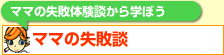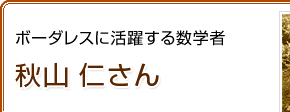  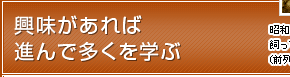 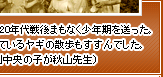
なぜ数学が一番好きで、得意だったのでしょうか。何かきっかけがありますか? どんな教科でも下手ながらやっているのは、動機があるから。算数だと、おもしろいと思う大きな原動力は、解けた時の快感。他の科目に比べて算数は覚えることが少ないし、少ない知識で何とかなる。中学生くらいで勉強していた本当の理由は、もてたかったから。『不良だけど頭がいいやつ』と友達(特に女友達)に思われたかったんですね。国語や社会ができるのは真面目な努力家というイメージでしたから。優等生で成績がよくてもそれほどのことではないけれど、『危険な香りのするやつなのに数学ができる』ことに「もてる」原点を感じた。いつも勉強しないで軽く一番取っているようで、実は隠れて勉強していました(笑)。やらなかったらできませんから、誰だってそうだと思いますよ。 自ら進んで好きなこと、やりたいことを見出せるのは子ども自身の力もあるでしょうけれど、その環境にいる大人の責任もありますね。 子どもへ物事のおもしろさを知らせるコーディネーター役が、親や先生だと思います。一旦何かを好きになれば、ほおっておいても子どもはどんどんやる。『算数を好きにさせるために、どうしたらいいですか?』とよく聞かれますが、物づくりやパズルなどでおもしろさの真髄をどこかの段階でしっかり体感させれば、あとは親も先生もいらない。 なるほど。今、ゲームや携帯が日常に当たり前にあって、その処理能力=筋道を立てて考える力のようにつながっています。算数に強い子の伸ばし方は、どのような導き方があるのでしょう? ただペーパーテストができても生活に応用できなければあまり意義はありません。 悔しいという思いが、今の子どもたちが普通に生活していてもなかなか体験できません。好きなことで競争して敗れて、泣いて初めて掴める力があるのかもしれませんね。 えらい人になるためには2種類あります。一つは、才能に恵まれ、その才能を伸ばして人生をつくる人。もう一つは、才能はなくても、なりたくてなる人生。前者のケースは皆に平等に与えられているとは限らない。才能なんて誰でもめったに無いものだから。でも後者のケースは、可能性に溢れている。努力すれば誰でもできるのですから。才能は後からしっかりついてくる。教育は、努力の尊さを教えることに尽きるかもしれません。 |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
子供の習い事トップ > ブログ・コラム・特集 > シリーズ・この人に聞く!第54回 > 2
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||